
<2018年2月18日追記>
最近、検索からこちらの記事に流れていらっしゃる方が多いようです。
初めましてm(_ _)m
というわけではなく、この記事では無勉強の人が一夜漬けだけで合格を狙うのは難しい、という趣旨でございますので、ご注意ください。ギリギリ勉強時間が足りなかったかもー。と思ってる方に向けた内容となります。
そもそも証券外務員資格試験とは?
証券外務員って聞いたことがありますか?
ほとんどの人が馴染みの無い言葉かと思いますが、証券会社や銀行などの金融商品を販売している金融機関等に所属する方は、ほぼほぼ必須で資格を取得しております(一部の業務や雇用形態等によっては取得してなくても大丈夫)。
「お客さんに金融商品を勧める以上、ちゃんとルールに従ってやるんだよ?」ということを定めたものであり、証券会社等に勤めている人は、このルールを定めている「日本証券業協会」なる団体に試験の合格を経て「証券外務員」として登録されて初めて、実際の業務を行うことができるのです。
金融の仕事をしてみたい、と金融機関に転職すると、最初の研修のようなところで「○○までにこの試験合格しておいてくださいね」なんていきなりハードルを与えられます。
一般的に大手金融機関に新卒で入社すると、研修として全員で座学も受けたりと学校のように学べるところもあるようですが、転職だったり大手ではないところであれば、そこまでちゃんとしたカリキュラムはなく、市販の問題集やテキストをもらって「じゃあ頑張って!」って感じだと思います。
誰でも受けられるようになったけど、そこそこ難しい
それでこの証券外務員、以前は実務経験が無いと受けられないものだったのですが、2012年より誰でも受験することが可能となりました。
将来、金融系の会社に転職したい人などが事前に受験したりすることもあって、一般の方の受験者数も増えてきているようです。
しかしこの試験、意外とハードルが高くて、ネットで見ると色々情報が散らばっているのですが、全くの知識がない人が受かろうと思うと、20~100時間程度の勉強が必要になってくると言われています。めっちゃ時間にばらつきありますけど、暗記しなきゃいけないものも多いし、ごく簡単ですけど計算問題もあるので、そこら辺は元々の得意領域などにもよるかと思います。
金融ちょっといい話
ちなみに転職前に資格を取っておくと、面接や選考で有利になるかと言われると難しいところ。面接者が資格をすでに保有していると聞いた時、企画・マーケ系であれば「へー、真面目ですねー」くらいの印象でしかなかったりしますし(実務する前には必須で取らなきゃいけないし、この資格でスキルとかはうかがえないので)、バックオフィス系であっても「おぉ真面目ですね」という感じだったりするのではないかと。大手だったら新卒研修で取らされるくらいなので。
なので「資格をもっていると金融の転職に有利!」とまでは全然いかないレベルだと思いますので。
入社時研修の内容減らせるなぁくらいの差しかないので、「何故資格を取ったのか?」を合わせて自己PRできるように準備しておくのがコツです。
「資格お持ちなんですね?」→「将来的に金融の仕事に従事したいと考えており、できる範囲での勉強を進めていました」的なものとかですね。
あと、FP資格も合わせて取っておくと、「提供者側と投資者側の両方を勉強しておいて損はないかと思いまして」みたいな事をさらっと言えたら印象良いと思います。
私(ま)は20時間程度の勉強量
私は今回証券外務員一種試験を、約一ヶ月間で20時間程度かけて勉強し、一発合格いたしました。ただし、以下のような事前条件がありました。
○:10年くらい前に一種試験の勉強をしたことがあった(2回試験に落ちて断念)
○:直近はマーケティング系で近しい環境にいたので業法等の軽い知識のアップデートはあった
○:4年ほど前に金融先物取引業務外務員という似たような試験を受けていた
☓:地頭がよくなく暗記系は最も苦手
☓:計算問題がとにかく弱い。Excelに頼りすぎてたので手の計算だとすぐミスる
☓:勉強を開始したのが、15年間同居した猫と死別してすぐ
これ、最後の☓が本当に自分の中では最難関で。本来は3ヶ月くらいかけて試験を受ける計画だったのですが、ちょうどその頃、15年同居してた愛猫がガンにかかっての闘病生活となってしまい、仕事以外はすべて猫に時間を使っていたので、愛猫が天国へ旅立った後からの勉強スタートとなってしまい、実質1ヶ月間程度しか勉強時間取れなかったという事情があります。
正直、ペットロスから立ち直れてもない中で「仕事のために試験勉強せぃ!」言われても「もう仕事なんてどうでもいい(泣)」という思いしかなかったので、身を入れて勉強したのは2週間くらいじゃないかと思います。
とはいえ、20時間はある程度の知識がある状態じゃないと個人的には厳しいと思うので、もう少し余裕をもってスケジュールを組むのが大切だと思います。
一回テキストを何か買ってみて、「これなら○○時間くらいでいけるかも」とか感じてもらうのも良いのではないかと(いきなりやる気なくしそうですが)。
短時間で勉強量も少ない中で駆け抜けた方法
1.参考書的なものを一冊じっくりと読み通す
とりあえず何の知識もない状態では問題集だけというのも当然厳しいので、一冊は参考書的なものをじっくりと読み通していきましょう。
問題は
一般に、景気が良くなると金利が上がり、景気が悪くなると金利が下がる。
のような2択で○☓問題も多いので、テキストの内容まんまの問題も結構あって重要です。
この時に「さっと読んだくらいじゃ全然理解できん!」というところに、付箋を貼っておくのも良いでしょう。すぐに本が付箋だらけの気持ち悪い状態になります。
これだけでも5~10時間は使ってしまうと思います。
付箋を貼ったあたりで、参考書で「重要!」とか「ポイント!」みたいに書かれている部分の内容や公式はまぁ頑張って覚えるしかありません。どうしても公式や丸暗記が必要な部分もあるので、こればかりは難しいところです。
2.理想的には模擬試験集を3~5パターンを3周繰り返す。
で、短期合格型を実践されてる人のほとんどが模擬試験集の複数回しです。
模擬試験集は市販の問題集の最後に「模擬試験」のようなかたちで掲載されている事が多いです。こういった市販の問題集書籍も数種類はありますが、資格学校のTACの教材の問題集は非常に質が良かったです(まんまの問題もいくつか出ました)。
逆に模擬試験ではなくて問題集書籍の問題集の部分はやらないのか?というと、短期で受かりたいのであれば、あまり気にしなくていいのかもしれません。後述する通り、模擬試験でよく引っかかる部分があれば、その類似問題とかにも目を通しておくくらいになるかと思います。
模擬試験は1回通してやるのに2時間近くかかるかと思います。答え合わせとかを入れるとさらに。。
なので、模擬試験集5種類×3周×2時間=30時間と、これだけでも20時間を超えてしまいます。当然3周目とかになるとかなり問題も覚えてスピードも上がりますし、逆に3周毎回に2時間かけてじっくりと内容を覚えていれば、もはやそれだけで合格できる基準の知識量がついている気がします。
3.模擬試験で間違えた部分だけ、問題集やテキストに戻って繰り返す
合ってたところは余計な知識のアップデートはしない!もう間違ってたところを、同じ間違いだけしないように再度調べなおして納得して次に進むようにしていきましょう。
4.最後は一夜漬け
私は試験を金曜の午後14時スタートとかの回にしておいたのですが、木曜日は定時ダッシュで会社をあがり、試験場からすぐ近くのビジネスホテルに泊まって、22時前には仮眠して1時過ぎから試験直前まで10時間以上の一夜漬けで一気に模擬試験を時間の許す限りで続けていました。
結果的に事前にやっていた分も含めて模擬試験5種類を2周したくらいのところでフィニッシュでした。もう精神的に追い詰められていた私には、このぐらいしか術がありませんでした(泣)
ちなみに泊まったのはもちろん東横インです。
試験当日に気をつけること
早めに会場に行く
この証券外務員試験は、大学とかの講堂とかを借りて行うわけではなく、パソコン教室のような小さなところで、個別に受ける試験です。
で、だいたいその試験会場の場所がわかりにくい!オフィスビルの中面とかにあったりして、地図見ながら行っても、最後ビル内で迷うとかいうことも有りがちですので。
私がいった新宿の受験施設も、そのフロアに上がるためのエレベーターが他のエレベーターとは全然違うところに配置されていたので、一瞬焦りました。
ここまで子供の遠足的な事をお伝えするのは、遅刻に超厳しいからです。私が受験した時も受付時間1分遅れで到着した男性が非情にも追い返されてました。試験開始時間ではなく受付時間です。。
遅れて受けられないなんてお金の無駄ですし、次にまた受けようと思う気持ちに大きなダメージを与えるので、遅刻絶対厳禁なつもりで、早めに行くに越したことはありません。電車の遅延だって待ってくれませんので。
会場で最後「へー」と思うくらいでテキストを読む
早めに会場につくから時間が空くので、テキストをパラパラと見ておくと良いです。
きっと初めて見るような内容が結構目につきます。。が、それをあえて「え!?」と深掘りせずに「へー」とか思いながら、次に目を向けていきましょう。今更新しい事を覚えるのはこの時点で無理ですが、覚えている事の確認はできるはずなので、「確認」な気持ちで目を通しておくのはとても良いと思います。
甘いものと水分は事前に少量摂っておきましょう
何しろ最長2時間半の長丁場の試験です。
普段から試験慣れしてない人はひどく疲れますし、喉も渇きます。
途中でお手洗いには行きづらいので、あまり大量に飲むのもよくありませんが、喉はしっかりと潤したうえ、チョコレートなどで糖分を入れておくのもオススメです。
「後でチェック」欄は天使か悪魔か
試験画面では問題が出ている画面の隅に「後で確認」のようなチェックボックスがあります。
ここにチェックしておくと、あとでチェックした問題だけにショートカットできる機能なのですが、そんなに自分自身で「絶対合ってる」なんて確信ができる問題が少ないので、「多分これだと思うけど、、後でチェックしておこう」というレベルで使ってしまうと、問題の大半が後でチェックまみれになってしまいます。
これもまた人にもよるのでしょうが、私は問題を読んで、「あ、これ怪しい」と思ったら回答も考えずにチェックを付けて、とりあえず一通りの問題を先に終わらせました。
途中の問題で詰まっている間にも、どんどんと頭の中から一夜漬けした内容が失われているイメージなので、一瞬前まで覚えていたものを失わないように、ここは必死こいて進めていき、最後の問題まで行ったあとで「後でチェック」の問題にじっくり取り掛かりました。
「回答終了」を押した瞬間に合否が出る
そんなこんなで2時間の辛い戦いを終わらせて、最後に「回答完了」のようなボタンを押すと試験が終わります。終わります、というか「回答終了」を押した瞬間に合否が出てしまいます。食い気味に来られてるくらいの勢いで出るので驚きます。
ただよくよく読まないと、合否はわからないのですが、ちゃんと書いてあるのでここで全ての結果が判断されます。。
試験を終えたら画面の指示に従って受付に戻ると、今度は紙ベースで結果を受け取りご帰宅となります。
新卒の人やちゃんと勉強したい人は真似しちゃ駄目
というわけで、私のようにブランクがあって知識を戻したい人や、もう効率重視でてっとり早く受かりたい人以外は、このような勉強法は向いていないと思います。
私自身「回答終了」を押す時は完全に落ちたイメージだったので、合格と出た時には我が目を疑いました。だいぶ運が良かったようです。
実際に金融系のお仕事につかない限りは、あまり利用する価値のない資格だとは思いますが、今後そちらへの転職などをお考えの方や、実際に転職して急に試験を受けなければならなくなった方などは、参考にしてもらえたら幸いです。
どうぞよしなによろしくお願いします。
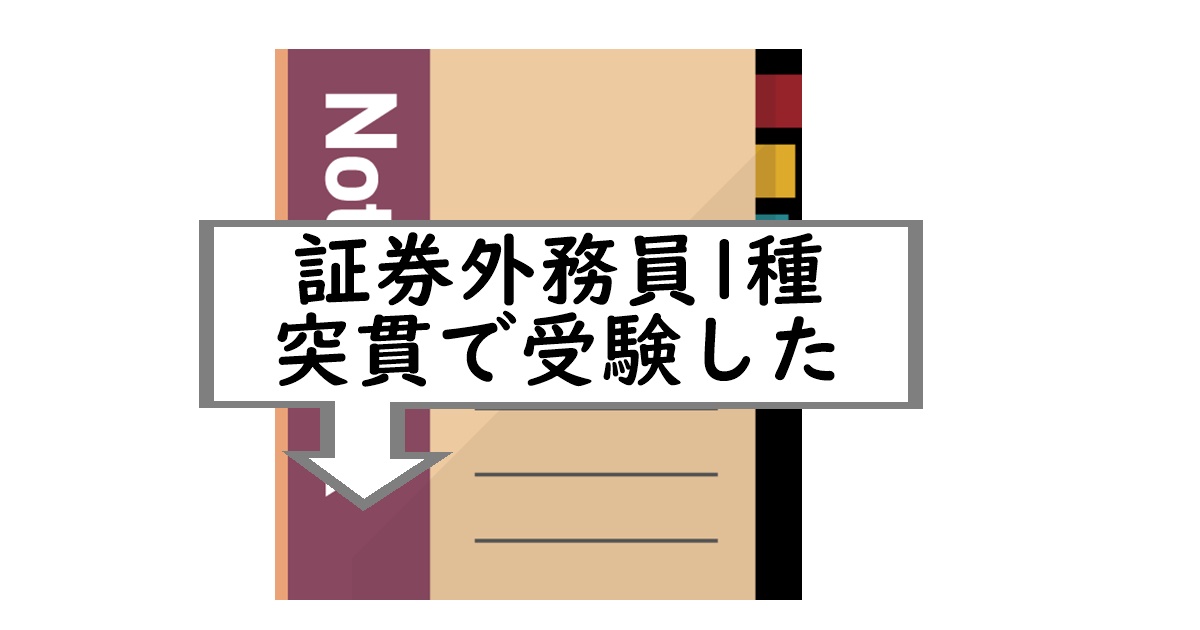

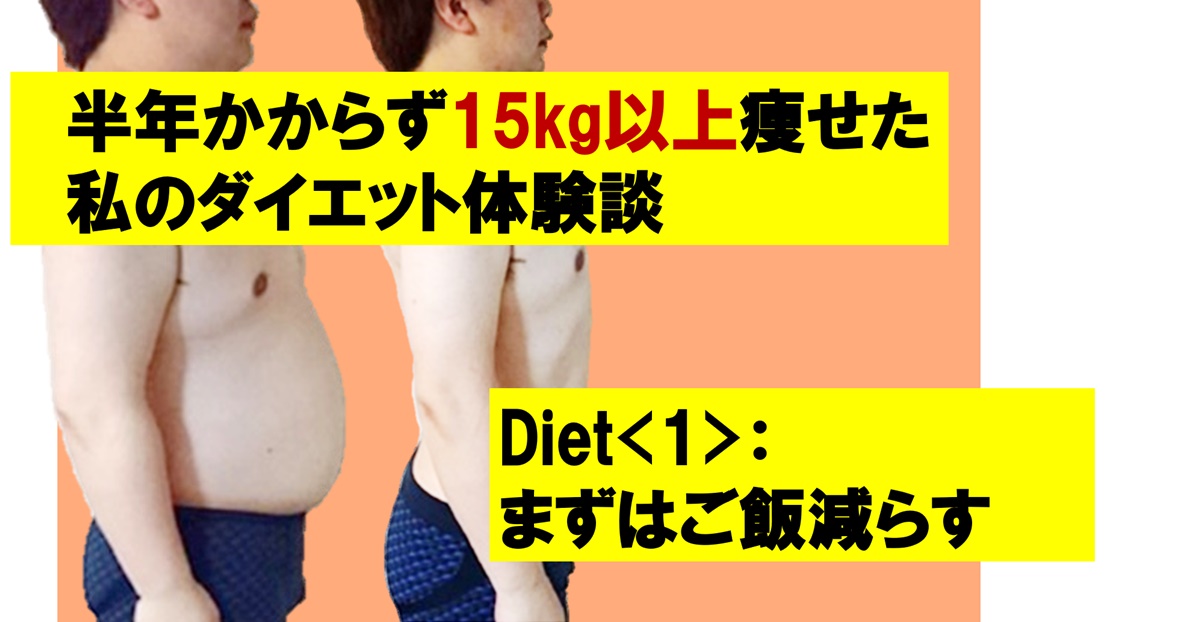
コメント